
北部師団とメキシコ革命その1
80年余り昔、メキシコは革命の嵐の中にあった。粗末な服にソンブレロをかぶり、弾帯を袈裟掛けにした農民兵がその主役だった。そして農民兵の後ろには、必ず兵士たちの妻の大群が子供を抱えて続いていた。当時、メキシコの農民の大半は大農園で働く雇われの農業労働者だった。大変に貧しい生活の上に、大抵の場合彼等は主人から借金を背負わされてもいた。そんな農民が兵士になれば、その妻は、夫の属する部隊の後ろをどこまでも、例え戦場でさえ付いて歩くしか生きる道がなかった。従軍女(ソルダデーラ)と呼ばれるメキシコの軍隊(革命軍と政府軍とを問わず)独特の現象である。かくも貧しい農民が、そこまでして革命軍に身を投じたのは何のためだったのだろうか。
1
フランシスコ・ビジャとアルバロ・オブレゴン。メキシコ革命を代表するこの二人の軍事指導者の軍が激突したのは、1915年4月6日、場所はメキシコ市から北西に 200kmほどの町セラヤであった。ビジャが率いたのは護憲軍北部師団2万2千人、野砲30門以上。オブレゴンの兵力は護憲軍北西師団1万1千、野砲13門、機関銃86挺であった。つまり、先日まで同じ旗の下に戦って来た仲間同志の対決だったである。
もっとも、ビジャが敵意を燃やした本当の相手はオブレゴンではなく、オブレゴンの上司である護憲軍の「第一統領」ベヌスティアノ・カランサであった。 片や人生の大半を馬上で過ごした馬賊上がりの荒くれ男で、三十過ぎまで読み書きもできず、ひたすら大金持ちに対する敵意を武器に、貧しい農民が土地を手に入れられるためだけに戦った戦争の天才ビジャ。片やクリオージョ(スペイン系白人)の大農園主で、軍事的才能は皆無ながら政治力を駆使して革命派の最高指導者にのしあがり、貧者のための社会改革にはまったく無関心なカランサ。たまたま独裁者ウェルタ将軍という共通の敵が両者を結び付けていただけで、その敵が倒れた時、二人の間に破局が訪れるのも当然の成り行きだった。
だが、政治家カランサは決して戦場には出て来ない。だから、カランサ打倒を目指すビジャは、まず軍事面で彼を支えるオブレゴンと戦わねばならなかったのである。前述のように、兵力も火力もビジャ派が優勢だった。しかも、ビジャと北部師団の戦歴は輝ける勝利で埋められていた。何と言っても、革命軍がウェルタ将軍の政府軍に勝利した、その最大の功労者は北部師団であった。神出鬼没の用兵、巧妙な作戦、そして騎兵の壮烈な突撃によって、破竹の勢いで政府軍を追い詰めるビジャは、「常勝将軍」と呼ばれた。その頃、ビジャ以外の革命軍諸部隊は、オブレゴンの北西師団もパブロ・ゴンサレスの北東師団も政府軍と一進一退の戦いを繰り返していたというのに、である。
かつてウェルタ将軍の政府軍を蹴散らし、ついにビジャの名を聞いただけで政府軍の兵士が浮き足立ち、士気が萎えたという北部師団の猛烈な突撃が先日までの同志オブレゴンの北西軍にむけて襲い掛かった。
↓独裁者ポルフィリオ・ディアス大統領
 2
2
話はセラヤの決戦の5年前に遡る。メキシコはポルフィリオ・ディアス大統領の30年余りの統治下にあった。彼は、もとは1860年代のフランス干渉戦争の際の救国の英雄であったが、1877年に大統領になってからは、反動的な政策と反対派への弾圧を繰返す独裁者と化していた。その間、しかしメキシコは史上空前の経済発展を遂げたように見えた。大規模に外資が導入され、鉄道が国中に敷かれ、農業生産は急増した。
だが、無原則な外資導入により、鉄道、石油石炭、鉱山など主要産業は全て外国資本の配下に置かれた。そして、経済発展の恩恵に浴したのは一部の特権階級だけで、農民の多くは逆に貧しくなって行った。
もともとメキシコの先住民の農民たちには土地の所有などという概念がなく、彼等は村ごとの共有地を分けあって耕していた。もちろん、登記などされていないから、法的な所有権などは曖昧だった。ディアス政権は、そのような土地を合法的に強奪するため、所有権のはっきりしない土地を政府が接収し、大農園主や外国企業に払い下げるという法律を制定した。接収された土地の大半は先住民の共有地で、その面積は、合計で国土面積の1/4(日本の国土面積より広い!)にも達した。
この希代の悪法によって、政府と大農園主は大いに潤ったが、農民のほとんどは、自分たちの土地を失いペオン(大農園の農業労働者)と化した。以前から、メキシコは大農園主の支配する国ではあったが、それでもまだ少なからぬ先住民が、狭い土地を共有し合う貧しい生活ながらも、一応は自作農だった。だが、こうして土地を強奪された結果、ディアス政権の末期には、メキシコ総人口の84%を占める農民のうち、99.5%は自分の土地を持っていなかったのである。土地を取り戻そうとする農民の戦いは、全て政府軍や大農園主の私兵による血の弾圧で報われた。だから、農民は半ば奴隷の境遇に黙って耐えるしかなかった。耐えられない者どうするか、彼等は山賊になった。フランシスコ・ビジャも、ペオンの息子に生まれ、農園主に反抗したためにお尋ね者となった山賊の一人であった。
メキシコのバブル崩壊は1907年に起きた。米国の不況の道連れになって輸出が低迷し、それまで羽振りの良かった大農園主の中には経営の苦しくなる者もでてきた。多くのペオンが職を失い路頭に放り出され、鉱山労働者を中心に労働争議が頻発した。ディアス大統領は80才を越えて既に老い、側近の操り人形と化していたが、1910年の大統領選にまたも立候補する。
この時、最大のライバルとなったのが、大農園主出身の穏健な改革派フランシスコ・マデーロであった。彼は「ディアス再選反対同盟」を組織し、急速に支持を拡大していった。
このままでは選挙に負ける、とディアスは思ったのだろう。民主選挙の仮面をかなぐり捨てて露骨な選挙妨害に走った。マデーロは逮捕され、サン・ルイス・ポトシ市の監獄の中で投票日を迎えた。選挙が終わり、保釈されたマデーロは直ちに米国へ亡命、ディアス政権への宣戦布告である「サン・ルイス・ポトシ綱領」を発表して反乱に立ち上がった。1910年10月25日、メキシコ革命の長い長い戦いが始まったのだ。
3
マデーロは冴えない小男だった。しょせんは裕福な大農園主で、しかも戦争が下手ときていた。血を見るのが何よりも嫌いな菜食主義者で、新興宗教の教祖のように神がかったところがあり、「神が私に乗り移って手を動かし文章を書かせている」と称していた。演説が天才的にうまかったらしく、「彼が話し始めるとペオンたちは背中を向けた。だが話しが終わる頃には彼等は涙を流していた」ともいう。大金持ちの御曹司なのに、農民の間にカリスマ的人気があった。
そのマデーロが米国で武器を集め、いざ蜂起という時、集まった同志はたった4人だけだったという。彼は失望して米国へ引き返してしまった。だが、これはマデーロの大変な勘違いだった。確かに米国で旗揚げした彼の下に現れた同志は4人だけだったのだが、その間にメキシコ国内では大変なことになっていたのだ。
11月18日、メキシコ市の東 150kmのプエブラで、武器を集めて反乱の準備を行っていたマデーロの同志の一人アキレス・セルダンが、警察に踏み込まれて射殺された。革命最初の戦闘だった。セルダンの家は現在革命博物館となっており、警察との銃撃戦のあった2階は、弾痕の残る家具やセルダンの用意していた小銃などがそのまま展示されている(はっきり言って大変な豪邸である)。これを機に、革命の炎はあっというまにメキシコ全土に燃え広がっていた。
メキシコ市の南に隣接するモレーロス州ではメキシコ革命を代表するもう一人の革命家エミリアーノ・サパタが、大農園主に奪われた村の共有地を取り戻すため、マデーロ支持を唱えてゲリラ戦を始めた。そして北部のチワワ州で立ち上がった革命軍の中にはフランシスコ・ビジャの姿もあったのである。
反乱は失敗と思って米国に逃げ帰っていたマデーロは、これを見て驚いた。驚いているうちに、革命軍の有能な指揮官たちが、米国との国境の要衝シウダー・ファレスを占領してしまった。マデーロは何もしていないというのに、革命軍が勝ってしまったのだ。ディアス政権の内側は既に腐り果てており、ファレス市が陥落すると、ディアスの取り巻き連は動揺し、マデーロと裏取引をしてディアス一人を生贄に体制の維持を図ることにした。魚心に水心で、マデーロも直ちに革命戦争を中止し、政府と休戦協定を結んだ。衰えも著しい老独裁者は、「ディアス退陣」を叫ぶ反政府集会に激怒して軍と警察に発砲を命令、二百人の市民を殺戮した。だがその翌日、彼は取り巻きに説得されて辞任し、フランスに亡命した。
1911年5月、マデーロはディアスに代わって大統領に就任する。だがそれで物語が完結した訳ではない。
 ←革命ののろしを上げたフランシスコ・マデーロ
←革命ののろしを上げたフランシスコ・マデーロ
4
ディアス独裁政権を打倒して大統領となったマデーロを、民衆は歓呼をもって迎えた。
「ビバ!マデーロ!ビバ!ラ・デモクラシア!(マデーロ万歳!民主主義万歳!)」
「ところで友よ、皆が呼んでいるデモクラシアってのは一体何者だい?」
「そりゃマデーロ様のお隣におられるご婦人に決まってるさ。」
マデーロは政治的民主主義を求めて革命を起こしたが、農民たちが彼の革命に参加したのは、あくまでも今日食べるパンと、明日の食べ物を収穫する土地のためであった。ところが、マデーロは一見民主的な制度を整えてメキシコを「近代化」することには関心があったが、農地を貧農に配分することには何の関心もなかった。なぜなら、進歩的な自由主義者とは言いながら、しょせん彼もまた大農園主の一人だったからである。当然、農民への土地の分配を求めて革命を戦った諸勢力から不満が沸き出してくる。最初に爆発したのはモレーロス州の農民革命家エミリアーノ・サパタであった。彼は農地改革を要求してマデーロと何度も交渉したが、返事は常に曖昧ではっきりせず、結局のところ農地改革は実施されなかった。ついに両者は決裂し、マデーロはサパタが武装解除に応じないことを非難して、サパタ派討伐に乗り出す。
サパタは激怒した。「(大農園主に)強奪された土地・森林・水利などの財産は、正当な権利を有する村及び人民が直ちに保有するものとする。」と謳った「アラヤ綱領」を発表してマデーロ政権との対決を宣言する。サパタの革命軍討伐のために送り込まれたのはビクトリアノ・ウェルタ将軍である。もともとディアス政権下の軍人で、マデーロ政権下でも引き続き軍の実権を握っていた。彼はモレーロス州に乗り込むと、サパタ派鎮圧のため、数々の残虐行為を引き起こした。
サパタに続いて、革命の一番の功労者だったにもかかわらず、高い地位に就けなかったパスクァル・オロスコ将軍が、今度はサパタとは反対に保守派の大農園主たちにそそのかされて北部で反乱を起こした。これもウェルタ将軍が鎮圧に出動した。
オロスコは、ビジャと似た境遇の出身で戦友でもあったため、ビジャにも反乱への参加を誘った。だが彼はマデーロに心酔しており、反乱への参加を拒否し、ウェルタ将軍の鎮圧軍に准将の階級で加わった。ところが、ウェルタ将軍はこの馬賊から成り上がった革命派の准将を気に入らなかったらしい。反乱の鎮圧が終わると、ビジャは理由も定かではないまま突然ウェルタ将軍に逮捕され、形だけの裁判で銃殺を宣告される。あるいは、ウェルタは、近い将来、この男が自分の強力な敵となることを見抜いていたのかもしれない。
マデーロは政治家として数々の欠点があったが、大金持ちの大農園主にもかかわらず、意外にもこの山賊上がりの勇敢な戦士とは親友同士であった。ウェルタ将軍がビジャを処刑しようとしていることを知ると、彼は驚き大統領命令で処刑を中止させる。そのとき、ビジャは刑場に引き出され、銃殺隊が弾丸の装填を終え、狙いをつけるところであった。すんでのところで彼は命拾いをした。
5
間一髪命を救われたビジャは、結局刑務所に入れられるだけで済んだ。それまで読み書きを習ったことがなかった彼は、この時刑務所の中で初めて読み書きを習得する。教えたのは法廷書記官と、同じ監獄に投獄されていたサパタ派の幹部だった。政府軍准将の地位にある三十過ぎの男が、小学生のように教科書を目の前に掲げ、たどたどしく読んだという。
読み書きを覚えると、ビジャにとって、監獄の中にいる意義がなくなった。意義がないからと勝手に出られないのが監獄のはずだが、彼にそんな理屈は通用しない。読み書きを教えてくれた法廷書記官の手助けでビジャは脱獄し(この法廷書記官カルロス・ハウレギはそのままビジャの革命軍に参加してしまった。そして数々の戦いを最後まで生き抜き、長寿を全うした)、米国に高飛びする。
その間、国内ではさらにいくつかの散発的な反乱が続いた。マデーロ大統領に、メキシコを統治して行くための政治的な手腕がまったく欠けていることは明らかだった。そしてついに1912年2月9日、とうとう首都でまで反乱が勃発する。「悲劇の10日間」と呼ばれる惨劇の始まりだった。
国立宮殿に迫った反乱軍は、マデーロ大統領の弟グスタボ・マデーロの指揮する政府軍にひとまず撃退された。だが、グスタボの後を継いで反乱鎮圧の命を受けたウェルタ将軍は、なかなか反乱を鎮圧できなかった。いや、実は、ウェルタ将軍は反乱軍と裏取り引きをして、「鎮圧するふり」をしていたのである。その一方で、マデーロ大統領に忠実な部隊に対しては、反乱軍への無謀な突撃を命令して大きな犠牲を出させ、その力を削いでいた。その目的が何であるかは、おおよそ見当がつこうというものである。グスタボ・マデーロは、ウェルタ将軍を信用するな、と兄に注意を促すが、お人よしのマデーロ大統領は信じようとしなかった。
2月18日、それまで反乱軍を鎮圧するそぶりを見せていたウェルタ将軍が、マデーロ大統領に反旗を翻す。まずマデーロの弟グスタボが捕らえられて惨殺され、マデーロ自身も逮捕された。「正当的」に権力を奪取したいウェルタは、マデーロを脅迫して辞任を迫り、米国の駐メキシコ大使も、マデーロに「米国はウェルタ政権を支持している」と告げた。結局、反革命の本当の首謀者は米国だったのだ。
マデーロは脅迫に屈し、命の保障を条件に大統領辞任を承諾する。ウェルタ将軍はまず外務大臣に就任、そしてマデーロと副大統領ピノ・スアレスが辞任した。なぜ外務大臣かといえば、当時のメキシコの法律の規定では、正副大統領が辞任した場合、外務大臣がその職を継ぐ事になっていたからである。自動的に大統領に就任したウェルタは、しかし命の保証というマデーロとの約束を守る気はなかった。22日マデーロとスァレスは殺される。
6
ウェルタは大酒のみだが有能な軍人で、様々な計略にも長けていた。しかし、メキシコ革命全体を見渡したとき、彼は「小策士」以上の者ではなかった。彼には、一連の政変の下に流れる農民の巨大なエネルギーが目に入らなかった。それまで数限りなく繰り返されて来た政変同様、権力を握って不逞の輩を弾圧すればいいと考えていた。
だが、ウェルタの反革命は農民の激憤を買った。それまで散々無能をさらけ出していたマデーロは、死んだ途端に英雄に祭り上げられた。そして、ウェルタ新政権への服属を拒否したコアウィラ州知事ベヌスティアーノ・カランサを筆頭に、チワワ州のフランシスコ・ビジャ、ソノラ州のアルバロ・オブレゴンなどが一斉に打倒ウェルタの兵を挙げ、カランサを第一統領とする「護憲軍」を結成した。それとは別にエミリアーノ・サパタも引き続き戦い続ける。メキシコ革命第2幕の始まりである。
革命軍の中で最大の活躍を見せたのはフランシスコ・ビジャの護憲軍北部師団である。彼の功績により、もともと国民の支持などまったくないウェルタ政権は次第に追い詰められていった。だが・・・。
後年ロシア革命のルポ「世界を揺るがせた10日間」でその名を知られる米国人ジャーナリストのジョン・リードが北部師団に同行し、ビジャを密着取材していたのは、丁度この頃である。ビジャは、リードの質問に対して、自分はカランサの忠実な部下であると自認していた。だが、実のところ、彼はこのときまだカランサと直接会ったことがなかったのだ。ビジャとカランサ双方を取材したリードは、両者の立場も気質も決して相いれないことを看破する。後にリードの予想は的中した。
「俺は感激して彼の体を抱いた。が、二言三言言葉を交わしただけで俺の血は凍り付いてしまった。・・・彼の話全てが、我々の出身の違いを俺に思い知らさせるために費やされた。」カランサとの初対面を振り返ってビジャは語っている。両者の関係はこのあと加速度的に悪化し、そして共通の敵ウェルタが倒れると完全な破局が訪れたのである。
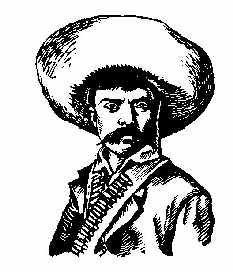 ←農民革命家エミリアーノ・サパタ
←農民革命家エミリアーノ・サパタ
7
山賊から革命軍の首領にのし上がったフランシスコ・ビジャは、1914年12月、護憲革命軍北部師団を率いて、ついにウェルタ将軍の政府軍を完全に打ち砕き首都メキシコ市に進軍する。先の独裁者ディアス同様、ウェルタもヨーロッパに逃亡する。革命軍の勝利であった。
だが、このときすでに革命軍の中で「第一頭領」カランサと北部師団を率いるビジャの対立は決定的になっていた。ビジャの活躍を快く思わないカランサは、政府軍との戦いの真っ只中に北部師団に足止め命令を下したり、鉄道を駆使して移動や補給を行う北部師団を妨害しようと石炭の供給を止めたり、護憲軍の他の二個師団、北西師団と北東師団を「軍」に格上げして北部師団だけ師団のままにしておく、などの嫌がらせを行ったが、ビジャの勢いを押しとどめることはできなかった。
ビジャの北部師団がメキシコ市に入ると、カランサは東方の港町ベラクルスへ退避、それまでビジャとカランサの調停に心を砕いた北西軍のオブレゴンもカランサの側に付いて後を追った。
メキシコ市には北からビジャの北部師団、南からエミリアーノ・サパタの農民軍が迫り、12月4日、メキシコ市近郊の水郷の町ソチルミコで、この二人の偉大な農民革命家の会見が実現する。会場は小学校の教室だった。
会見の席上、もともと寡黙なサパタは勿論、普段は陽気で豪快なビジャも何故かおとなしく、最初のうち両者の会話は途絶えがちであったという。だが、カランサの名が出た途端、気まずい雰囲気は一変し、互いにカランサの悪口を言い合って話が弾んだ。両者はカランサ打倒を目指して盟約を結ぶ。そして翌々日、二人はそれぞれ軍を率いてメキシコ市に進軍し、市内を軍事パレードして国立宮殿に入った。
ビジャとサパタの幕僚たちは大統領謁見室に乗り込んだ。ビジャはふざけて大統領の椅子に腰掛けたが、サパタはその椅子を恐怖の目で眺め、座ることを拒んだという。実に暗示的な逸話である。この日もビジャとサパタは今後の協力を約して、固い抱擁の後に別れた。だがこの後、二人が再び相見えることは、ついになかったのである。
二人が友情を誓い合ったにもかかわらず、その後両派の反目が目立って来る。また、サパタ派の農民軍は軍律が厳しく、首都でも礼儀正しく行動したが、ビジャ派は軍律も何もあったものではなく、略奪暴行のし放題、しかも両派ともに行政手腕皆無ときたものだから、首都は大混乱に陥ってしまった。
サパタ自身は首都で国政を握る気などさらさらなく、さっさと根拠地モレーロス州に引き上げてしまう。一方のビジャも、蠢動を続けるカランサ派を追って軍を率いて出撃する。首都には、両派の妥協の産物である、何の実権もない臨時大統領だけが残された。サパタはまず農民であり、それから素晴らしい革命家でもあったが、政治家ではなかった。「(大農園主に)強奪された土地・森林・水利などの財産は、正当な権利を持つ村及び人民が直ちに保有するものとする」という単純明快だが激烈な彼の思想はメキシコ中の人々の心を捕らえたけれど、サパタ自身はモレーロス州の革命しか頭になかった。まして、首都で国権を握るなど、まったく関心がなかったのである。
一方ビジャは、思想などというものは特になかったが、サパタと違いメキシコ全土を視野に行動する戦略家で、天才的な軍人でもあった。だが、彼もまた本質は農民であって政治家ではなく、権力とか大統領の座とかに何の関心もないことはサパタと同じだった。政治的野心がない、ということは素晴らしい美点ではあるが、カランサという政治的野心の権化と戦うには、致命的な欠点となり得た。結局、政治的にはサパタは純粋すぎ、ビジャは幼稚すぎたのである。
8
そして1915年。この年はメキシコ史上最悪の流血の年となった。ビジャ率いる北部師団とカランサ派のオブレゴン率いる北西師団の決戦は、南北アメリカ大陸史上、米国の南北戦争に次ぐ大規模で凄惨な戦いであり、かつ信じ難いほどむなしい戦いでもあった。
ビジャやサパタにとって、革命の唯一の目的は大農園主から土地を取り上げて貧しい農民に分配することだったから、自ら大農園主で、有産階級のためだけの改革を目指していたカランサとは確かに相入れなかった。だが、カランサ派の将軍たちは、カランサ自身ほどには保守的ではなかった。彼等は、メキシコに土地改革が必要であることを承知していた。オブレゴン将軍も同じである。彼も大農園主出身ではあったが、カランサよりは遥かに進歩的で柔軟だった。オブレゴンは労働運動を味方につけることにも成功する。彼は労働団体と協定を結び、「赤色労働者大隊」を組織してビジャとの戦いに参戦させた。後年壁画家として、またメキシコ共産党の指導者として名を成したD.A.シケイロスは、前年、若干17歳でカランサ派に投じ、後に大佐まで昇進している。
一方、ビジャとサパタは貧しい農民の利益代弁者であったが、それがあまりに徹底していたため、都市の組織労働者を味方につけることができなかった。しかしサパタ派にも社会主義的な知識人がブレーンとして加わっていたし、前述のジョン・リード、後に「世界を揺るがした10日間」で不朽の名を残し、米国共産党の創設者にもなったこのジャーナリストは、メキシコで取材を始めた途端にビジャに心酔してしまい、密着ルポ「反乱するメキシコ」を書いている。
そして、ビジャ派もカランサ派も主力は農民兵であった。土地の分配を求めて革命を戦った農民兵の思いは、ビジャ派でもカランサ派でも同じであった。ビジャの北部師団には、アパッチ族、タラウマラ族など先住民諸族が部族ごとに参加していたし、オブレゴンの北西軍にはさらに多くの先住民部族が加わっていた。例えばヤキ族は、奪われた農地を取り戻すため、何度も反乱を起こしては鎮圧され殺され、捕らえられて奴隷として大農園に叩き売られてきた。メキシコ革命が始まった時、彼等は何度目かの土地回復の希望を賭けて、オブレゴンの北西軍に参加したのである。その彼等の思いに、ビジャ派と何か違いがあっただろうか。カランサを首領として認めるかどうか、ただそれだけのことで、今まで同じ旗の下に戦って来た同志たちが敵味方に分かれ、数万の死者を出したのである。
9
1915年1月、ビジャに追われてベラクルスに逃げていたオブレゴンは再び勢力を盛り返し、2月にはメキシコ市を占領した。しかし彼の軍があっさり首都を引き払ったため、3月には再びサパタ派が首都を奪回する。
オブレゴンにとって、首都を一時サパタ派に明け渡すなど大した問題ではなく、当面の問題はビジャと雌雄を決することだった。サパタ派は、たまたま首都に誰もいなくなったから出てきただけで、メキシコ市を死守しようという意思はさらさらなかったし、サパタ派はゲリラ部隊で、野戦で正面からぶつかったらビジャやオブレゴンの軍の敵ではなかったから、ビジャに勝ちさえすれば、メキシコ市など付録のようたやすく手に入れられたのである。北西軍は、各所で北部師団と激戦を繰り返しながら西進した。
これを迎撃すべくビジャの北部師団も南下する。ビジャの幕僚フェリペ・アンヘレス将軍は、オブレゴンと不用意に戦わないよう忠告したがビジャは聞き入れなかった。
メキシコ革命にはやたらと将軍が出て来るが、実は、メキシコでは誰でも自己の才覚で兵士を数百人集めれば、一夜にして「将軍」になれたのだ。兵士は昨日までの貧しい農民や労働者で、読み書きができればそれだけでただちに将校にされた。その中にあってアンヘレスはディアス政権下で士官学校校長を務めた本物の将軍である。彼はマデーロ政権時には心ならずもサパタ派討伐軍を指揮したが、ウェルタが反革命で政権を奪った際は協力を拒否、カランサの護憲軍に参加して、後にビジャの北部師団に転じた人物で、人格高潔かつ優れた作戦家であった。ビジャとは個人的友情で結ばれ、後にアンヘレスがカランサ派に捕らえられて処刑された時、ビジャは声を上げて泣いたという。だが、この時に限って、ビジャはこの優れた幕僚の忠告をことごとく無視している。
4月4日、北西師団はセラヤに布陣する。だがオブレゴンは、戦場がセラヤよりさらに西のイラプァトになると見込んでいた。しかしこれは読み違いだった。翌5日、北部師団がサラマンカに布陣しているとの急報がもたらされる。予想よりはるかに手前で敵は待ち構えていたのである。このとき、北西軍の前衛部隊は既にセラヤから18kmはなれたグアヘまで前進していた。敵はまだずっと先と思って様子見に先行した前衛部隊は、知らないうちに圧倒的に強力な敵の目の前に飛び出してしまったのだ。
オブレゴン配下の将軍の一人は、この戦いについて「オブレゴン将軍の戦った戦闘の中で、これほど不運な始まり方をしたものは他にない」と語っている。この日、ビジャは北部師団の閲兵を行なった後、翌6日未明、3隊に分かれてサラマンカを出撃して、まずグアヘに向かう。北側をアグスティン・エストラーダ将軍の騎兵部隊、南側をアベル・セラトス将軍の騎兵部隊が進み、中央部をホセ・エロン・ゴンサレス、ディオニシオ・トリアナ、ブランカモンテス、サン・ロマンの諸将が率いる歩兵部隊とその後方から砲兵隊が進軍しだ。
夜明け、北部師団は北西軍前衛のマイコッテ旅団とグアヘで激突した。北西師団前衛旅団はビジャの騎兵隊の壮烈な突撃に圧倒され、あっという間に蹂躙されていった。状況は絶望的で、旅団長マイコッテ准将はオブレゴンに救援を要請せざるを得なかった。オブレゴン自身が1500人の増援を率いてグアヘに急行するが、正午過ぎ、増援部隊がグアヘに着いたとき、すでに前衛旅団は壊滅的打撃を受けていた。
それでも、オブレゴンとマイコッテは、部隊が総崩れになることを防ぎ、整然と撤退してきた。16時、彼等はセラヤに帰還する。オブレゴンはカランサに電報を送る。「マイコッテは現在苦戦しております。私自身が歩兵部隊と機関銃隊を率いてやっと脱出して来たところです。この戦いは不利です。